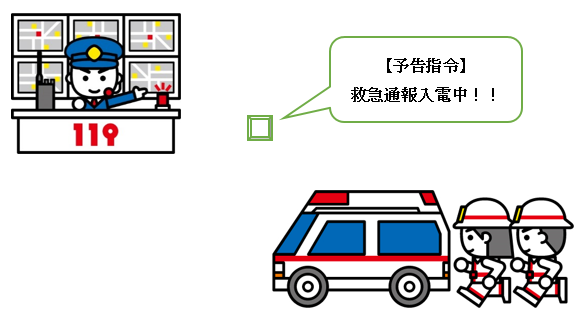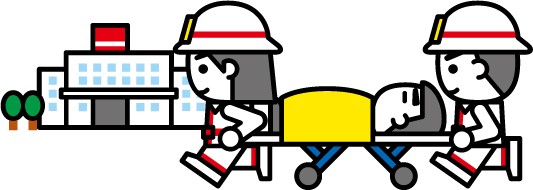消防を少しでも身近に感じてもらおうとの思いから始まった、この「ほのおのにっき」‼
今では170名の全職員が広報マンとなり、それぞれの誕生日に近いところで日記をアップしています。もちろんトップである消防長も・・・(笑)
そして、その内容は「最終的に消防に関心が寄せられるようなもの」とする多少の縛りはありますが、趣味、時節柄の出来事、食事のレシピ、地区の出来事や話題、所属でのブーム、消防に関するマニアックな解説等々本当に多岐に亘っており、驚きや感心させられるもの、思わずほくそ笑むようなものまで様々です。
職員一人ひとりが、知恵を搾って少しでも親しみと関心を持ってもらえるよう文章を作るということは、少なからず文章力、プレゼン力のアップに繋がっているのでは??と思っています。
さて、そんな中、いよいよ私の投稿順が回ってきました。実は私、この3月末でいよいよ42年の消防人生に幕を閉じることとなり、最後はこの関連で締めくくろうかと考えていましたが、奇しくも私の退職と合わせたように、4月末で「平成」の時代が終わり、5月からは新しい元号に変わることとなり、今の元号と同じ地区名を持つ地域(旧武儀町)に住む私としては、「一つの時代が終わる」という一抹の寂しい思いとともに、「新たなスタート!」という点で “偶然にも重なったこの事態” に対し強く共感を持ち、今回は「平成の終わりを迎える我が地元」について書かせていただきます。
今この地域では、平成の最後ということで、新聞やテレビ等で地域の様子が幾度となく取り上げられています。
何と!大晦日のNHK「ゆく年くる年」では、美濃清水と呼ばれる「日龍峯寺」が冒頭と末尾で放映され、まさに全国区!(笑) この日以来参拝者が急増したとか・・・。
また、「道の駅平成」でも、終わりゆく平成時代を惜しむかのように観光客が押し寄せ、30年前の「平成フィーバー」を彷彿させる賑わいを見せており、平成にあやかった様々な商品が飛ぶように売れているそうです。
その他にも「ありがとう!平成時代」と銘打って、様々な感謝イベントが計画されています。元旦には平成最後の「平成山で初日の出を見る会」が行われ、私も孫たちを連れ参加してきました。
今後も、「平成最後の日の入を見る会」、「新元号 Sun-Riseを見よう!」などの企画を現在計画中と聞いています。
みなさんも平成の出来事に思いを馳せ、これからのイベントに参加してみませんか。
私も、これまでの時代(消防人生)に感謝し、新しい時代(第2の人生)の幕開けに心弾ませています。