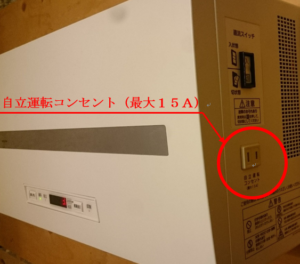みなさんが趣味と聞いて思い浮かべるものは、多々あると思います。
「筋トレ、釣り、キャンプ、登山、サーフィン・・・・」
そんな中、私の今一番の趣味となっているのが、最近入会したジムへ通うことです。
今までは、市営のジムへ通いトレーニングを重ねてきましたが、
どうしても水泳がしたい!!!という気持ちがこみ上げてきたため、この度水泳のできるジムへの入会に踏み切りました。
では、なぜ水泳なのか?と聞きたくなりますよね?
それは・・・、
アクアスロンに出場したいからです!!!
アクアスロン?なんだそれは?トライアスロンじゃないの?と思う方も多いでしょう。
アクアスロンとは、水泳+ランで順位を競う競技(トライアスロンの自転車を省いた競技)です。
小学校時代スイミングスクールに通い、大学まで長距離走を行ってきた私には勝負できる競技であると考えトレーニングを開始しました。
水泳は、日常生活であまり動かすことのない筋肉を使うため、陸上とは違った運動効果が期待できます。
さらに、体力の向上やダイエットに加えて、疲労回復、脳の活性化、うつ病軽減、風邪が引きにくくなるなどなど、健康促進につながるお得な効果が満載なのです。
消防士は当直勤務をするため、24時間消防署にいます。出動が多ければ睡眠不足や、疲労が蓄積してしまいストレスとなって自分に降りかかってきます。運動でストレスを発散する意味でもジムに通い、トレーニングに励むことはとても大切なことだと思います。
トレーニングを行うに当たり、消防士になる前と後では変わった点があります。
それは、トレーニングの目的を考えるようになったことです。今までは、ただやらされているトレーニングでしたが、今は、自分でどこを鍛えるためにどのようなトレーニングをすればいいかを考えるようになりました。
日々仕事をする中で、物事の根拠を考えるようになったからだと感じています。
来年度の出場を目標に掲げ、基礎からトレーニングをしていきたいと思います。
まずは3月に関市で開催される『関シティマラソン』のハーフマラソンに出場予定なので、そこに向けて頑張っていきます!!!!