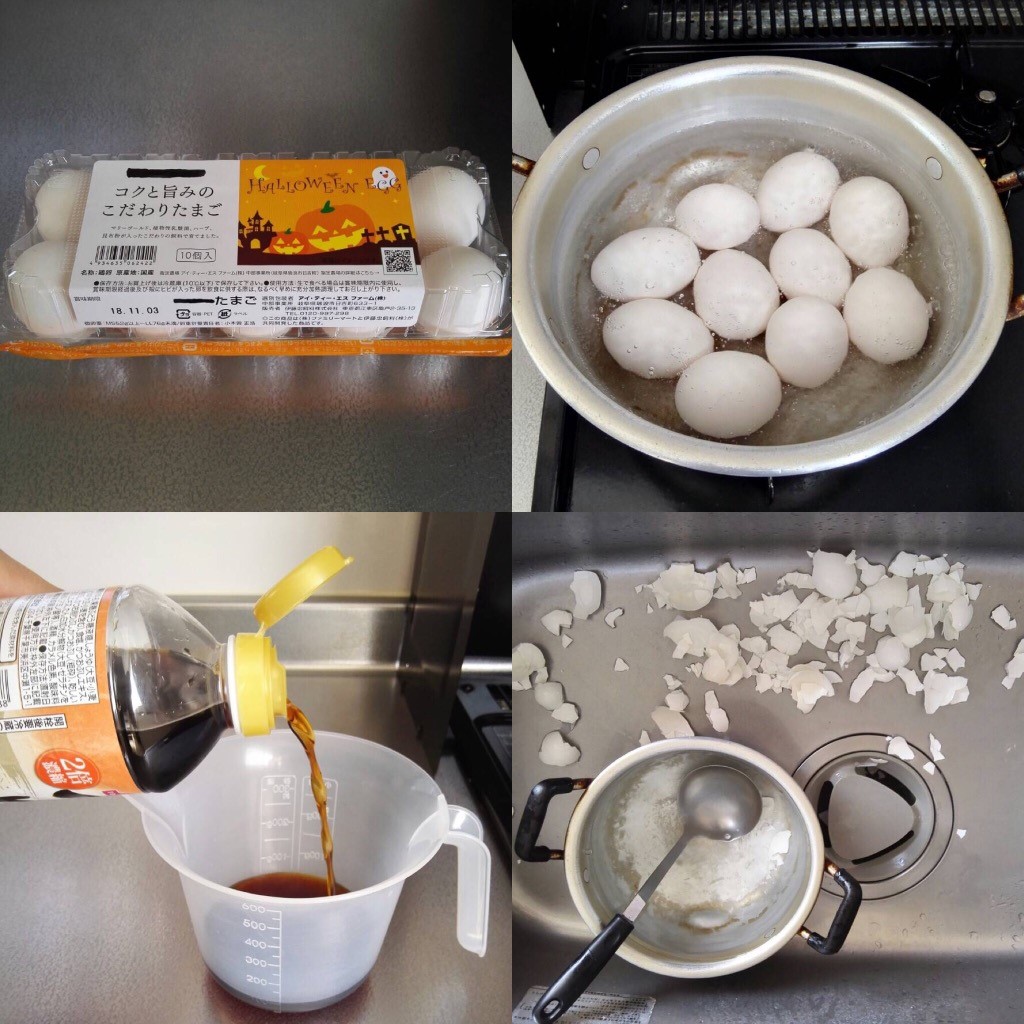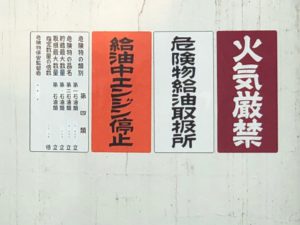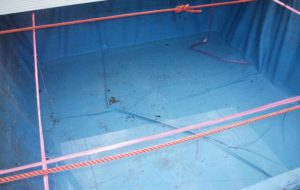消防士の趣味といったら、マラソン、登山、キャンプ等アウトドアなイメージがありませんか?
私の趣味は違います。私は2児の父でありながら、家でビデオゲームをすることが大好きなインドア消防士です。
みなさんのなかには「ビデオゲーム=ちょっとオタク=ちょっと気持ち悪い=子どもにはやらせたくない」といった、くら~いイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。
しかし、そんな考えはもう古いのです!みなさんは最近メディア等でe-Sports(エレクトロニック・スポーツ)と言う言葉を聞いたことがありませんか?これはビデオゲームで対戦することを「スポーツ、競技」として捉えたものです。高額な賞金がかけられた世界規模の大会も開催され、年収1億円を超えるプロゲーマーもおり、もはやビデオゲームはくら~い遊びではないのです。
私も対戦型のビデオゲームをプレイし勝つことに喜びを感じています。負けた時はその理由を考え反省し、事前の練習に加え戦術の考慮や武器の性能等を再確認するなど、勝利のために努力しています。私はビデオゲームをすることで目標を達成するために何をするべきかを考える力がついたと思います。
ここまでビデオゲームについて熱く語りましたが、消防業務を遂行するためにも、事前の訓練、活動方針の考慮、使用資器材の性能の把握、そして反省が大切です。一見全く違う分野に見えますが、目的を達成するために実施することは一緒であると思っています。
私は私らしく、趣味で培った「考える力」を消防業務に発揮していきたいと思います。
最後に私の子どもが大きくなり「ビデオゲームをやりたい」と言うようになったら、「中途半端にやるな!やるからには徹底的にやれ!」と指導したいです。