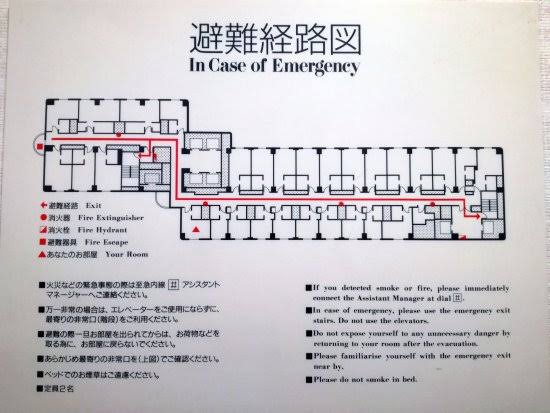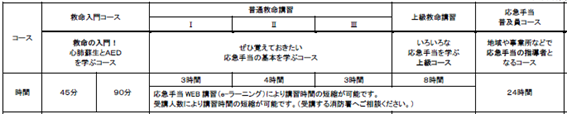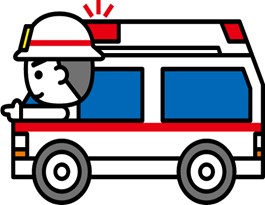今年の4月8日(月)から11月15日(金)までの
【延べ「222日間」 時間にして「1,256時間」】
一人前の消防士となるために勉強や厳しい訓練を積み重ねてきた3人が、岐阜県消防学校総合教育(消防士になるための登竜門)を終了し、無事に中濃消防組合に帰って来ました。
岐阜県消防学校では同期生3人で力を合わせ、厳しい学校生活を乗り越えてきました。
しかし、配属先では3人で勤務することはほとんどありません。早く消防という職業に慣れ、1人でも力を発揮できるように、現在は先輩の消防士から指導を受けながら努力をしている最中です。
新人ではありますが、新人だからといって失敗が許される職業ではありません。
新人だろうがベテランだろうが、住民の皆さんからしてみれば同じ消防士です。
3人からは
「早く住民の皆さんの期待に応えられる消防士になります!!」
と心強い宣言をもらいました。
新たに仲間に加わった3人を、よろしくお願いします!