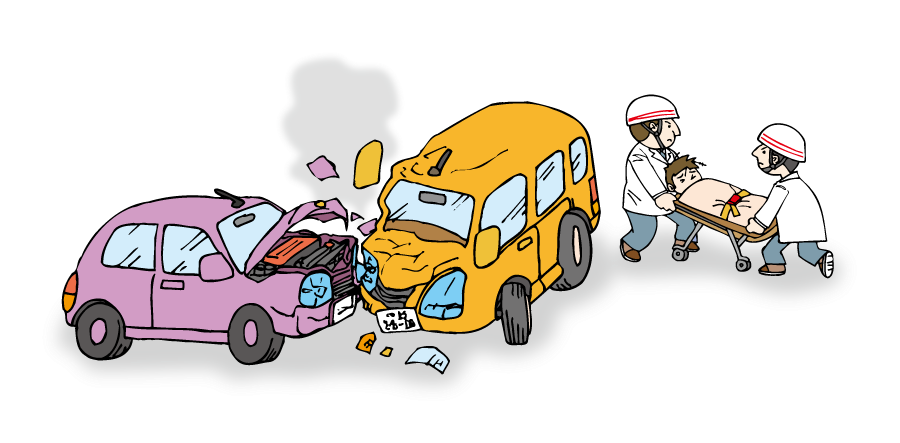誕生日が近くなり、運転免許の更新をしてきました。皆さんご存じかと思いますが、5年間無事故・無違反を達成するとゴールド免許となり、私は「優良運転者講習」を受講、所要時間は約30分となります。ブルー免許の場合はもう少し長時間の講習になるので、短い時間の講習でちょっと得した気分でした。
消防署で勤務していると何度も交通事故現場に遭遇し、そのたびに交通事故の怖さ、悲惨さを痛感することとなります。だからこそ、自分が事故の当事者にならないよう、これからも肝に銘じて運転しようと改めて強く思いました。
講習中に講師の方から交通事故を起こしてしまったら・・・というお話が。まずは、怪我人がいたら救急車を呼ぶこと。そして警察にも連絡を。怪我人がいた場合、救護義務が発生します。その場からいなくならないように・・・など。
私は指令課勤務をしていて、119番通報を受けたとき、事故をした場所をなかなか特定できない場合があります。とにかく慌てないこと、どうしていいか分からない場合は、誰か助けを呼ぶ、周りの人に通報してもらうなど方法があります。
119番通報すると、いろいろなことをこちらからお聞きします。私たちも上手く情報を聞き出す努力をしますので皆さんも交通事故に限らず119番通報する際は
「と・に・か・く!お・ち・つ・い・て」ください。
ご理解、ご協力をお願いします。