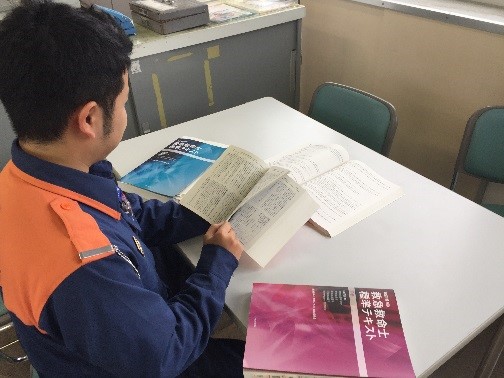自分では、少しだけ国語が得意な方だと思っている・・・。
しかし、読書は大嫌い!で興味のある趣味の雑誌くらいしか読まない。
読書家にはバカにされそうですが、とにかく読まない。
「最近、何か読んだ?」と聞かれても、・・・
・【八つ墓村】
みなさんご存知、横溝正史の推理小説で金田一耕助シリーズ、テレビドラマや映画にもなった。名セリフは「祟りじゃ〜っ! 八つ墓の祟りじゃ〜っ!」
・【連合艦隊の○○?】
本の題名が思い出せない、「○○の連合艦隊」だったのか、「連合艦隊の○○」だったかも思い出せない。内容は、終戦間際、日本帝国海軍連合艦隊の戦艦大和などが撃沈されるというお話のなかで、色んな人間模様や戦争のはかなさ、悲しさが描かれています。この手のものはテレビでも映画でも良く放映されましたが、私にとっては、可哀そうで、一番“うるうる”きますね!!中でも、1981年公開の映画「連合艦隊」はお気に入りで、レンタルビデオやテレビ放送で何度も見ました。また、谷村新司が歌う主題歌の「群青」も♪カラオケ♪お気に入りでした。
≪映画「連合艦隊」の悲しい名セリフのほんの一部(泣けます)≫
◎空母瑞鶴から戦闘機で飛び立つ予定の幼い搭乗員が「私たちは、発艦することは出来ても着艦はできません。出撃したらもう二度と帰ってきません。敵艦に体当たりします。」「折角整備してくださった大事なゼロ戦を壊してしまいますけど、許してください」と瑞鶴整備士長に訴える・・・
◎父の乗る沈みゆく戦艦大和に向かって「お父さん、親よりもほんの少しだけ長く生きていることがせめてもの親孝行です。」といって特攻に出撃する息子・・・
・【汚れた英雄】
オートバイレーサーの小説、草刈正雄が主演で1982年に映画公開、当然見に行きました。ローズマリー・バトラーの主題歌もカッコ良かった。
・【丹波哲郎の死者の書】
死後の世界を描いた霊界関係の本、後に「大霊界 死んだらどうなる」という名の映画になりましたが、その時のロケ地が当消防本部管内の旧板取村であったことから、当消防本部も救急車や救助隊員が少しだけ協力出演しています。1989年公開で、もう30年近くも前の事なので、この事実を知っている職員も少なくなってしまいました。ただし、ロケに参加した職員は「映画に出演した!」と言って喜んでいましたが、出来上がった作品を鑑賞したところ、映っていたのは走る救急車と救助服姿の足だけでした・・笑!笑!大笑!
・【謎のバミューダ海域】
ご存知、バミューダ・トライアングル。嘘か真か超常現象の起こる三角地帯のお話です。
・・・の5冊くらいしか思い浮かばないし、内容的にも趣味の域を越えることのできない映画にもなるような文庫本ばかりで、しかも、数十年も前のお話です。
どうも長い文章や活字が苦手で、心地よい睡魔が襲ってきます。
読んだり、聞いたりするより、話す方が好きだからでしょうか・・・。
そんな私は3年ほど前に大病を患い、二度の手術、入院もしましたが、それでも漫画本や趣味の雑誌ばかりを読んで、まともな文庫本など読みもしませんでした。
今でも、病院へは定期的に検査に行っていますが、皆さんもご存じのように、診察待ちや会計待ちで、ほぼ半日が潰れます。(某大学病院です)
それでも、まともな読書はせず、バイク雑誌を読んだりスマートフォンをいじったりしていましたが、この度、数十年ぶりに読書をしました。
その本の名は『 バ カ 論 』!!
やっぱり趣味の域を越えられなかった訳です!!
ネット上で知った文庫本で、著者がビートたけしだったので気軽な気持ちで読めるのかなって思い購入しましたが、思ったとおりさらっと軽く読めました。
著者なりの毒舌や持論、視点も鋭く、真面目なバカ論、いや立派な人生論かもしれないと勝手に納得し読みました。
皆さんもご存じの有名なお笑い芸人の事を「教養なき天才」と表現したり、『「国立阿片窟」を建設せよ』の話、『間抜けな「働き方改革」』の話では、思わず納得して吹き出してしまった。
決して、ためになる本、素晴らしい本、身になる本、感心する本、とは言いませんが、バカを承知で読むのも悪くはありませんよ。
私のいる消防とお笑いは全く違う世界だと思いますが、この「バカ論」のごとく、職場での鋭い視点や常識とは違う視点、観察力を磨きたいものです。
追伸
単行本なるものを数十年ぶりに自腹購入した訳ですが、結構するものですね!
税込777円のお支払でした。“意味深な価格設定”
もったいないので、もう1回読み返そうかと思っています。












 6 つき上がった餅をのし板に乗せ、のし棒で好みの厚さに伸ばし、のし餅の完成です
6 つき上がった餅をのし板に乗せ、のし棒で好みの厚さに伸ばし、のし餅の完成です 「薪ストーブは3回人を温める」と言われます。
「薪ストーブは3回人を温める」と言われます。 そして最後!これが一番大切なことかもしれません。みんなで働いて汗を流し、薪ストーブに焚かれた炎を囲み食事をとれば、消防活動をする上で必要なチームワークが高まること間違いありません!
そして最後!これが一番大切なことかもしれません。みんなで働いて汗を流し、薪ストーブに焚かれた炎を囲み食事をとれば、消防活動をする上で必要なチームワークが高まること間違いありません!